作品概要
来場者の方がクリスマスプレゼントを受け取れます。
作品解説
本作品を論理一貫して解説することはできません。
なぜなら、ある程度の直感に基づいて制作されているからです。
美術評論家のマイケル・フリードは「芸術は何かの表象ではない」と言いました。私はこれが必ずしも正しいとは思いませんが(また、このフリードはモダニスト流の意図でこの言葉を発したはずですが)、芸術がなぜ存在し、芸術以外では代替不可能であるかについての説得力のある論証だと言えます。
そこで作品解説にあたり、私が同作を制作するために自分に課したいくつかの「問い」を示したいと思います。
1.暴力と愛について
暴力を愛で肯定する!
どうすればそんなことがまかりとおるものでしょうか。
芸術における暴力は作家と観客の関係性のもとに生まれます。
全体主義国家や社会主義国家における芸術は国家の理念を体現するものであり、観客に対して一方的な関係性を強いるものでした。つまり、作家による独裁的暴力です。またその反動として、観客の能動性を呼び起こす芸術も生まれました。ここでは観客による民主的暴力が推奨されます。しかし、それにおいても「作家による扇動」が必要となるため、「独裁的に民主的暴力が生み出されている」という歪さがあります。
政治哲学者のジャック・ランシエールは『観客の解放』のなかでこの袋小路を指摘しました。
それと同時に、ランシエールは『民主主義への憎悪』のなかで、民主主義とは「寡頭制に対する絶え間なき反抗」であると言い、本質的に争いを引き起こすものだと言います。
現代において大きな課題となっているのは、独裁的暴力でしょうか、民主的暴力でしょうか?ネット上における暴力の多くは、作家が意図すらしていない「一方的な言いがかり」であり、それ自体は民主主義を象徴する行為です。しかし、それに際して起きた数多くの「自粛騒動」は、独裁的暴力だとも言えます。つまり、未だ袋小路を脱せていないのです。
私はこの現象の根源が、哲学者のハンナ・アーレントが指摘した、キリスト教、資本主義、マルクス主義といった西洋的価値観に共通する「なにかしら一つの正しさが存在する」という前提に起因すると考えます。
よって、西洋的価値観を離れ、あらたな政治形態、作家と観客の関係を見出すべきだと考えるのです。そして私は、「贈与」関係をその一つの可能性であると考えます。
未開部族社会における贈与関係は、マルセル・モースが発見し、レヴィ=ストロースによって理論化されました。部族同士は、過剰なほどの物品を贈与し合うことで連帯を保つのです。そして、ストロースは部族間の「嫁入り」を贈与の一形態と位置づけました。しかし現代は、血縁や地理による共同体=コミュニティが失権し、興味・関心による共同体=アソシエーションの連なりによって再構成されはじめた社会だと言えます。
翻ってみると、「嫁入り」とはコミュニティの中では連帯のための装置だと言えても、アソシエーションにおいては愛の帰結にほかなりません。
連帯は暴力を寛容によって受け止め、連帯は愛によって実現します。そして、贈与は愛と同じ力を持つのです。つまり、アソシエーション同士の贈与関係こそが、現代における西洋的価値観の暴力を乗り越える可能性を持つのではないか、と私は考えるのです。
2.芸術について
カール・マルクスは人間の営みを「労働」として一元化しましたが、そこで哲学者のハンナ・アーレントが抱いた危機感は、機械工業化が進んでいくなかで「労働」が人々の手から失われ、人間の価値がゼロに近づいていくということでした。そしてアーレントはマルクスを批判し、『人間の条件』のなかで「労働」を細分化して「労働」「仕事」「活動」などとして再定義しました。「労働」は個体が生きるために必要な営みであり、飲食や排泄、生きるための賃金労働などが含まれます。アーレントは労働だけを行う存在を「動物」と呼びました。続いて「仕事」は種が存続していくための営みであり、住宅や家具の制作などが含まれます。そして仕事だけをする存在を「神」と呼びました。そして、個体同士の交流を意味する「活動」をする存在として、アーレントは「人間」を条件付けました。
アーレントによれば、芸術は仕事に含まれます。
しかし、アーレントの師でもあるハイデガーは、『技術への問い』のなかで資本主義社会の本質が「ゲシュテル」に向かうこと、すなわり「あらゆることが有用性によって価値判断される社会」であることを看破しました。芸術も例外ではありません。この世界観では、芸術は有用性のある芸術、つまり非芸術化した芸術だけが残ります。西洋のアートマーケットの発展は、芸術がゲシュテルに向かったことを象徴する出来事でもありました。その後、その反動としてパフォーマンス・アートが出現します。非物質としての芸術は、アートマーケットに巻き込まれずゲシュテルを乗り越えることができると考えたのです。そして、それは「活動」の芸術化とも言えました。
2010年代の現代になると、住宅・家具・その他あらゆるものの消費財化、すなわち仕事の労働化が起きています。それを印象づけるのが、スローライフブーム、断捨離ブームです。スローライフは一般的に、戦後の大量消費崇拝への反動と位置付けられますが、よりラディカルな形態としての「生活そのものの消費財化」に他なりません。
そして芸術において起きているのは、パフォーマンス・アートすらも各地の芸術祭のなかで客寄せイベント化し、ゲシュテルに巻き込まれてしまっていることです。つまり、活動の労働化であり、非物質芸術の非芸術化です。そしてその反動として、「物質としての作品」への回帰、つまり仕事への回帰が起きています。あらゆるものが労働化するなかで、仕事の復権を目指しているのです。しかし、この試みすらも1980年代のニューペインティングによって試みられ、失敗した先例の繰り返しです。
このあべこべな状況は打開しなければなりません。そして、現代において芸術を行うこと自体の不可能性を問うことが必要なのです。
そこで私は、労働の芸術化に可能性を見出します。
つまり、仕事=確固たる物質としての芸術ではなく、活動=非物質の芸術ではなく、労働=消費財としての芸術を希求すべきではないか。私は、その問いを発してみたいと思うのです。
3.『パッタイ』について
拙作「聖夜の贈り物」は、タイ出身の芸術家であるリクリット・ティラバーニャの作品『パッタイ』を下敷きとしています。『パッタイ』は、ティラバーニャが焼きそばを調理して観客に振る舞うという作品です。美術批評家であるニコラ・ブリオーの『関係性の美学』のなかで、『パッタイ』が現代における芸術が持つ作家と観客の関係性を象徴しているとして評価されました。またモダニストによって、『パッタイ』は「焼きそばを観客に渡す姿が美的である」として評価されています。
しかし私は、焼きそばを「贈与すること自体が良い」のではないかと考えます。そしてそれと同時に課題として捉えられるのが、パッタイとはタイ料理であり、すなわちコミュニティを表象していることです。
冷戦後、国際政治学者のサミュエル・ハンティントンが『文明の衝突』のなかで予言したのは、未来の戦争が政治思想ではなく、コミュニティ同士の衝突によって起きるということでした。そしてそれは2010年代の現代において現実のものとなっています。よって、現代において『パッタイ』が持つ政治性は争いを助長してしまうのです。
我々は、これをいかにして乗り越えるべきでしょうか。
1,2,3は、一つの大きな問題系として繋がっています。しかし芸術は、その答えを持ちあわせていません。
芸術とは、アーレントによれば「世界を拡張する」営みであり、その可能性を示すことです。
「聖夜の贈り物」は、その可能性の一つを示すことができるのではないかと思うのです。
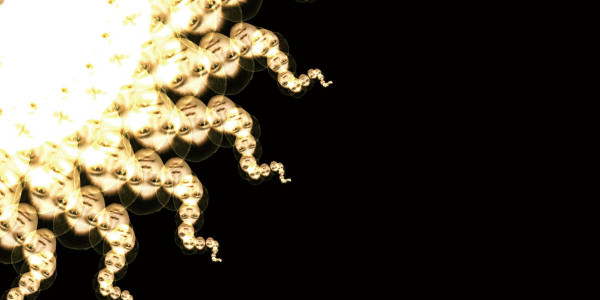


 Follow
Follow